「副業で収入を得たけど、確定申告って必要なの?」
「税金のことなんて全然分からない…難しそう…」
「もし間違えたらどうしよう…ペナルティとかあるの?」
副業を始めた喜びも束の間、「確定申告」という言葉に、漠然とした不安や難しさを感じていませんか?ご安心ください。確定申告は、ポイントさえ押さえれば決して怖いものではありません。
この記事を読めば、副業の確定申告に関する疑問や不安が解消され、スムーズに手続きを進めるための知識が身につきます!
今回は、副業における税金の基本から、確定申告が必要なケース、具体的な手続きの流れ、そして節税に繋がるポイントまで、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。
これを機に確定申告への苦手意識を克服し、安心して副業ライフを送りましょう! 💪
🤔そもそも確定申告とは?なぜ副業で必要なの?
まずは基本の「き」。確定申告とは何か、なぜ副業をしていると関係してくるのかを理解しましょう。
確定申告とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得(儲け)と、それに対する所得税などの税金の額を計算し、国(税務署)に報告・納税する手続きのことです。
会社員の場合、通常は会社が年末調整で税金の計算と納税を代行してくれるため、個人で確定申告をする必要がないことが多いです。しかし、副業で一定以上の所得がある場合は、年末調整ではカバーしきれないため、自分で確定申告を行う必要が出てきます。
💡 副業で確定申告が必要になる主な理由
- 年末調整では副業の所得が考慮されない:会社は本業の給与についてのみ年末調整を行います。副業で得た所得は自分で申告する必要があります。
- 正しい税額を納めるため:所得が増えれば、納めるべき税金も増える可能性があります。確定申告をすることで、正確な税額を計算し、納めすぎや未納を防ぎます。
- 還付金を受け取れる場合がある:納めすぎた税金がある場合、確定申告をすることで還付金として戻ってくることがあります(医療費控除やふるさと納税など)。
つまり、確定申告は「面倒な義務」というだけでなく、「正しく税金を納め、場合によっては払いすぎた税金を取り戻すための大切な手続き」でもあるのです。
💰副業の所得って何?収入との違いは?種類も解説!
確定申告を理解する上で重要なのが「所得」という言葉です。「収入」とは違うの?どんな種類があるの?といった疑問を解消しましょう。
「収入」と「所得」の違い
この2つの言葉は混同しがちですが、意味が異なります。
- 収入:売上や給料など、入ってきたお金そのもののこと。
- 所得:収入から必要経費を差し引いた金額のこと。いわゆる「儲け」の部分です。
所得 = 収入 - 必要経費
確定申告で計算するのは、この「所得」に対する税金です。
事業所得・雑所得(多くの副業が該当)
フリーランス型の副業(Webライター、デザイナー、コンサルタント、ブログ運営、ハンドメイド販売など)で得た所得は、主に「事業所得」または「雑所得」に分類されます。
事業所得とは?
反復・継続・独立して行われる仕事から得られる所得。一般的に、ある程度の規模感があり、継続的に行っている事業から得られる所得が該当します。青色申告ができるのは原則として事業所得(または不動産所得、山林所得)です。
雑所得とは?
他のどの所得にも当てはまらない所得。副業の規模が小さい場合や、単発的な収入の場合は雑所得に分類されることが多いです。近年、副業の所得区分については税制改正の議論もあり、判断が難しいケースもあります。
どちらに分類されるか?:明確な線引きは難しいですが、一般的には「事業として本格的に取り組んでいるか」「継続性・安定性があるか」「帳簿書類を保存しているか」などが判断基準になります。迷ったら税務署や税理士に相談するのが確実です。2022年分の確定申告から、事業所得か雑所得かの判断基準が一部明確化されています。
給与所得(アルバイト・パートなど)
副業としてアルバイトやパートをしている場合、そこから得られる収入は「給与所得」となります。これは本業の会社から受け取る給与と同じ扱いです。
給与所得の場合、通常は給与から源泉徴泉(税金が天引き)されており、年末調整で精算されます。しかし、複数の会社から給与を得ている場合や、年間の給与収入が一定額を超える場合は、確定申告が必要になることがあります。
🎯【重要】あなたは確定申告が必要?判断基準をチェック!
副業をしている全ての人が確定申告をしなければならないわけではありません。ここでは、主に会社員の方が副業をしているケースを想定して、確定申告が必要になる主な基準を解説します。
⚠️ 確定申告が必要になる主なケース(会社員の場合)
- 副業の所得(収入-経費)が年間20万円を超える場合:
これが最も一般的なケースです。ここでいう「所得」は、事業所得や雑所得などを指します。複数の副業をしている場合は、それらの所得を合計して20万円を超えるかどうかで判断します。
- 2か所以上から給与をもらっていて、年末調整されなかった給与収入と各種所得(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合:
例えば、本業の会社とは別に、副業でアルバイトをしていて、そのアルバイト先で年末調整が行われなかった場合などが該当します。
- 本業の給与収入が年間2,000万円を超える場合:
この場合は、副業の所得に関わらず確定申告が必要です。
- 医療費控除や住宅ローン控除(1年目)、ふるさと納税(ワンストップ特例制度を利用しない場合)などで税金の還付を受けたい場合:
この場合は、副業の所得が20万円以下であっても、還付のために確定申告をすることができます(または、した方が得です)。
注意点:上記の「所得20万円以下なら申告不要」というのは、所得税の話です。住民税については、所得の多少に関わらず申告が必要です。所得税の確定申告をすれば、その情報が市区町村にも連携されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。しかし、所得税の確定申告をしない場合は、別途お住まいの市区町村役場で住民税の申告が必要になるので注意しましょう。
⚖️確定申告の種類:青色申告と白色申告どっちを選ぶ?
副業の所得が事業所得または不動産所得、山林所得に該当する場合、確定申告の方法として「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分に合った方を選びましょう。(雑所得の場合は白色申告のみです)
🔵 青色申告
事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出することで選択できる申告方法です。複式簿記での帳簿付けが必要など手間はかかりますが、税制上の大きなメリットがあります。
✔ メリット:
- 青色申告特別控除:最高65万円または55万円、10万円の所得控除が受けられる(要件あり)。これにより所得が圧縮され、税金が安くなる。
- 赤字の繰り越し:事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、黒字と相殺できる。
- 家族への給与を経費にできる:青色事業専従者給与として、生計を同一にする配偶者や親族への給与を必要経費にできる(要件あり)。
- その他、減価償却の特例など。
✘ デメリット:
- 事前の申請が必要:原則として、その年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)に申請書を提出する必要がある。
- 複式簿記での帳簿付けが原則:日々の取引を正規の簿記の原則に従って記録し、貸借対照表や損益計算書を作成する必要がある(会計ソフトを使えば比較的容易)。
- 手間がかかる。
こんな人におすすめ: 副業を本格的に事業として成長させたい、節税メリットを最大限に受けたい、会計ソフトの利用に抵抗がない。
⚪ 白色申告
青色申告の申請をしていない場合、自動的に白色申告となります。帳簿付けは簡易的なもので済みますが、税制上の特典は青色申告に比べて少ないです。
✔ メリット:
- 事前の申請が不要。
- 帳簿付けが比較的簡単:簡易簿記(単式簿記)でOK。日々の収入と支出を記録する程度で済む場合が多い。
- 手間が少ない。
✘ デメリット:
- 青色申告特別控除のような大きな所得控除がない。
- 赤字の繰り越しができない(一部例外あり)。
- 青色事業専従者給与の制度がない。
こんな人におすすめ: 副業の所得が少ない、帳簿付けに時間をかけたくない、とりあえず確定申告を済ませたい。
副業の所得が年間300万円以下の場合は、2022年分から帳簿の保存要件が緩和されるなど、白色申告でも対応しやすくなっていますが、節税効果を考えると、可能であれば青色申告(特にe-Taxによる申告で65万円控除)を目指すのがおすすめです。
🗺️【ステップ解説】確定申告の準備から提出までの流れ
「具体的に何をすればいいの?」という方のために、確定申告の準備から提出、納税までの一連の流れをステップごとに解説します。
1 必要書類の準備と帳簿付け 📊
いつから?:年間を通じて(1月1日~12月31日)
何をする?:
- 収入に関する書類:売上が分かるもの(請求書控え、売上管理表、支払調書など)、給与所得がある場合は源泉徴収票。
- 経費に関する書類:領収書、レシート、クレジットカード明細、銀行振込控えなど。
- 控除に関する書類:生命保険料控除証明書、医療費の領収書、国民年金保険料控除証明書、iDeCo掛金払込証明書、ふるさと納税の寄付金受領証明書など。
- 帳簿付け:日々の取引(収入、経費)を記録します。白色申告なら簡易簿記、青色申告なら複式簿記。会計ソフト(freee会計, マネーフォワード クラウド確定申告, やよいの青色申告 オンラインなど)を利用すると効率的です。
ポイント:領収書やレシートは月ごとにまとめて封筒に入れるなど、整理して保管しましょう。会計ソフトは無料プランから試せるものも多いので、自分に合ったものを選びましょう。
2 所得と税額の計算 🧮
いつ?:確定申告期間前(例:翌年1月下旬~2月上旬)
何をする?:
- 1年間の収入と経費を集計し、所得金額を計算します(収入 – 経費 = 所得)。
- 各種所得控除(基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)を計算し、課税所得金額を算出します(所得 – 所得控除 = 課税所得)。
- 課税所得金額に所得税率を掛けて所得税額を計算し、そこから税額控除(住宅ローン控除など)を差し引いて、最終的な納税額または還付額を算出します。
ポイント:会計ソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、指示に従って入力するだけで自動的に計算してくれる部分が多いです。所得税の税率は累進課税(所得が高いほど税率も高くなる)です。
3 確定申告書の作成 📝
いつ?:確定申告期間中(通常、翌年2月16日~3月15日)
何をする?:計算した所得や税額を、確定申告書に記入します。
- 確定申告書A・Bの区別(令和4年分まで):以前は申告書A(主に給与所得者や年金所得者向け)と申告書B(所得の種類に関わらず誰でも使える)がありましたが、令和4年分以降は申告書Bの様式に一本化されました。
- 作成方法:
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でオンライン作成(推奨)。
- 会計ソフトで作成。
- 手書きで作成(税務署や市区町村役場で用紙を入手)。
- 青色申告の場合は、青色申告決算書(損益計算書、貸借対照表など)も作成します。
ポイント:「確定申告書等作成コーナー」は質問に答えていくだけで書類が作成でき、e-Taxでの電子申告にも対応しているので非常に便利です。
4 確定申告書の提出 📤
いつ?:確定申告期間中(通常、翌年2月16日~3月15日)
何をする?:作成した確定申告書と必要書類を税務署に提出します。
- e-Tax(電子申告):マイナンバーカードとICカードリーダーライタ(または対応スマホ)があれば、自宅からオンラインで提出可能。添付書類もデータで送れる場合があり、還付も早い傾向。青色申告65万円控除の適用にはe-Taxが必須(または電子帳簿保存)。
- 郵送:管轄の税務署宛に郵送。信書扱い。控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封。
- 税務署の窓口へ持参:直接税務署の受付に提出。相談も可能だが、期間中は非常に混雑する。
ポイント:提出期限間際は混雑するので、早めの準備・提出を心がけましょう。e-Taxは便利なので、マイナンバーカードを持っている方はぜひ挑戦してみてください。
5 納税または還付 🏦
納税期限:通常、確定申告期限と同じ3月15日。
還付時期:e-Taxなら2~3週間程度、郵送や窓口提出なら1ヶ月~1ヶ月半程度が目安。
何をする?:
- 納税の場合:
- 振替納税(口座引き落とし、事前に手続きが必要)。
- クレジットカード納付(国税クレジットカードお支払サイト)。
- コンビニ納付(QRコードまたはバーコード)。
- 金融機関や税務署の窓口で現金納付。
- ダイレクト納付(e-Tax利用)。
- 還付の場合:確定申告書に記載した銀行口座に、税務署から還付金が振り込まれます。
ポイント:納税が遅れると延滞税がかかる場合があります。振替納税は一度手続きすれば翌年以降も自動で引き落とされるので便利です。
✂️副業で経費にできるものは?賢く節税するコツ
副業の所得を計算する上で重要なのが「必要経費」です。経費を正しく計上することで、所得が圧縮され、結果的に税金が安くなります。どんなものが経費になるのか、具体例を見ていきましょう。
🧾 副業で経費にできる可能性のある主な項目
- ブログ運営費(サーバー代、ドメイン代、WordPressテーマ代)
- パソコン、スマホ、周辺機器の購入費(事業用割合に応じて)
- インターネット通信費、電話代(事業用割合に応じて)
- ソフトウェア購入費、クラウドサービス利用料
- 書籍代、セミナー参加費、教材費(スキルアップのため)
- 打ち合わせ時の飲食代(会議費)
- 交通費(取材、打ち合わせなど)
- 広告宣伝費(ブログ広告出稿など)
- 文房具、事務用品費
- 外注費(記事作成代行、デザイン依頼など)
- 家賃、水道光熱費(自宅で仕事をしている場合の按分経費)
- 振込手数料
- 取材費
- その他、副業収入を得るために直接かかった費用
※上記はあくまで一例です。実際に経費として認められるかは、その費用が「副業収入を得るために直接必要であったか」が判断基準となります。
💡 経費計上のポイントと注意点
- 領収書・レシートは必ず保管:経費の証明となるため、日付、金額、支払先、内容が分かるように保管しましょう。感熱紙のレシートは文字が消えやすいので、コピーを取ったりスキャンしたりするのも有効です。
- 家事按分(かじあんぶん):自宅で仕事をしている場合、家賃や水道光熱費、通信費などを、事業で使用した割合に応じて経費にできます。按分割合は、仕事部屋の面積や使用時間など、合理的な基準で設定します。
例:家賃10万円、仕事部屋が全体の20%を占める場合 → 10万円 × 20% = 2万円を経費に計上。
- プライベートな支出との区別:事業に関係のない個人的な支出は経費にできません。明確に区別しましょう。
- 高額な固定資産(パソコンなど):購入金額が10万円以上のものは、原則として減価償却という方法で数年に分けて経費計上します。ただし、青色申告者であれば30万円未満のものは「少額減価償却資産の特例」で一括経費にできる場合があります。
- 帳簿への正確な記録:いつ、何に、いくら支払ったかを正確に帳簿に記録することが大切です。
💰 その他の節税のコツ
- 青色申告を選択する:前述の通り、最大65万円の特別控除は大きな節税効果があります。
- 所得控除を漏れなく活用する:生命保険料控除、医療費控除、iDeCo(個人型確定拠出年金)、小規模企業共済、ふるさと納税など、利用できる控除は積極的に活用しましょう。
- 予定納税の活用:前年の所得税額が一定以上の場合、翌年分の所得税を前払いする「予定納税」の制度があります。資金繰りを考慮して対応しましょう。
- 税理士に相談する:所得が大きくなってきた場合や、判断に迷うことが多い場合は、税理士に相談するのも一つの手です。費用はかかりますが、適切な節税アドバイスや申告代行を依頼できます。
🚫確定申告しないとどうなる?ペナルティについて
「面倒だから」「バレないだろう」と確定申告を怠ると、思わぬペナルティが課される可能性があります。どのようなペナルティがあるのか、正しく理解しておきましょう。
😱 主なペナルティ(加算税・延滞税)
- 無申告加算税:期限内に確定申告をしなかった場合に課される税金。原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合で課されます(税務調査を受ける前に自主的に申告した場合は軽減されることもあります)。
- 過少申告加算税:申告した税額が実際より少なかった場合に課される税金。追加で納める税額の10%(場合によっては15%)が課されます。
- 重加算税:事実を隠蔽したり、仮装したりして意図的に税金を少なく申告した場合など、悪質なケースに課される最も重いペナルティ。無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%の税率。
- 延滞税:法定納期限までに税金を納めなかった場合に、遅れた日数に応じて課される利息のようなもの。税率は時期によって変動します。
これらのペナルティは、本来納めるべき税金に上乗せして支払う必要があり、大きな負担になりかねません。また、悪質な場合は刑事罰の対象となる可能性もゼロではありません。
税務署は、様々な情報から個人の所得を把握しています。「バレないだろう」という安易な考えは禁物です。必ず期限内に正しく申告・納税しましょう。
❓【Q&A】確定申告に関するよくある質問
最後に、副業の確定申告に関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。
まとめ:確定申告を理解して、安心の副業ライフを!
副業における確定申告は、一見すると複雑で難しそうに感じるかもしれません。しかし、基本的な仕組みや手順、そして注意点を理解すれば、決して怖いものではありません。
大切なのは、日頃から収入や経費の記録をしっかり行い、早めに準備を始めることです。会計ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーなどを上手に活用すれば、手続きの負担も軽減できます。
この記事が、あなたの確定申告に対する不安を少しでも和らげ、スムーズな手続きの一助となれば幸いです。正しい知識を身につけて、安心して副業に取り組み、充実した毎日を送りましょう!
これであなたも確定申告マスター! ✨

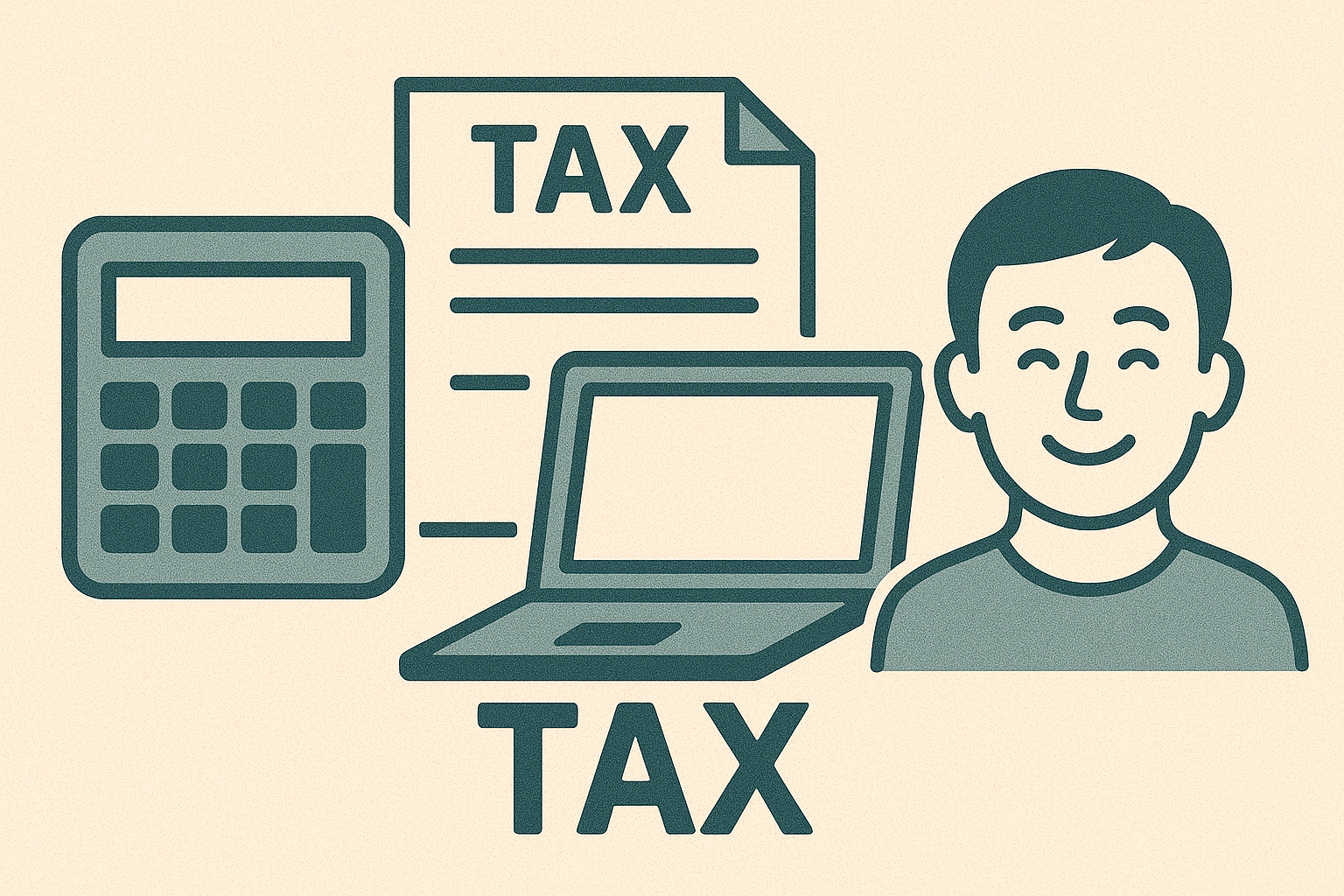
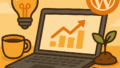

コメント